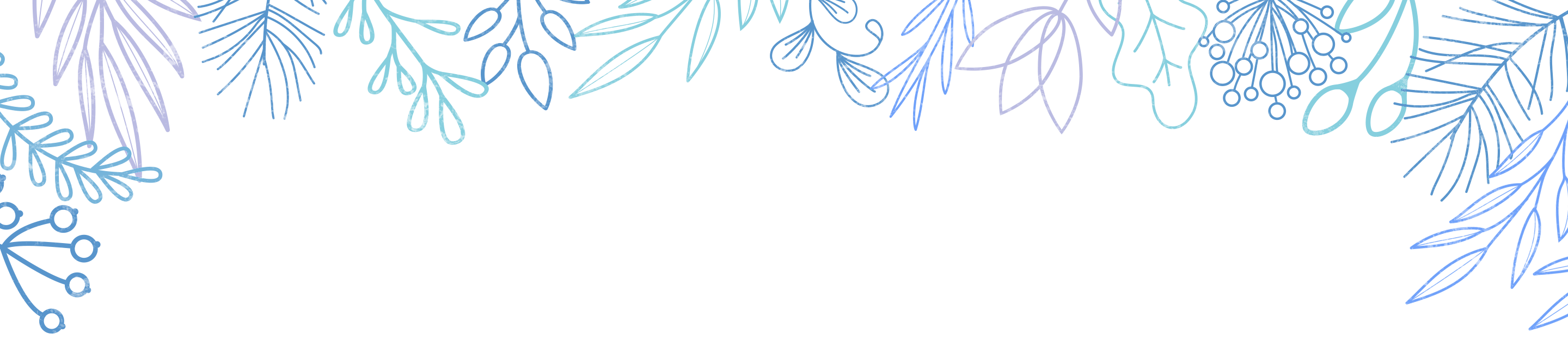こんにちは!ユミです。
10月はじめ頃に義祖母が亡くなり、バタバタしていましたが、やっと落ち着いてきました。
旦那側の初めてのお葬式だったので、分からないことが沢山ありました^^;
元々、あまりお葬式に出席したことがなく、(成人してからは1回くらい?)
経験もなければ一般常識もない私…。
義祖母でのお葬式では、できる限り失礼のないようにしたいと思いながら、私なりに頑張りました^^;
この記事では、お葬式後に気になったこと、
義理の祖父母の葬儀は忌引きになるのか?
義祖母が他界した年の年賀状は喪中はがきにするべきか?
の2点について書きたいと思います。
義理の祖父母の葬儀は忌引きになる?
義祖母が亡くなり、お葬式、初七日、四十九日を済ませたら、ちょっとホッとしますね。
四十九日はまだなのですが、旦那だけで行ってもらうことになりました。よかった^^;
すでに10月も終わりということもあり、年賀状の準備をする時期になってきました。
義祖母が亡くなった場合は忌引きになるのかな?
そんな疑問があったので、ちょっと調べてみました!
忌引きの意味
忌引きとは、「家族や親族が亡くなった時に喪に服すこと」
昔は、親族など近しい人が亡くなると、一定期間家にこもって故人を悼んだり穢れを落とす意味合いがあったんだとか。
最近では、忌引き休暇として会社からお休みを頂ける期間を指すときに使いますよね。
忌引き休暇の日数は?
忌引き休暇の日数は決まっていません。
それぞれの会社で決められた日数があります。
私の職場では、
- 1親等は2日、
- 血族の2親等は1日
だけしかもらえず、義祖母は忌引き休暇に該当しませんでした。
ですが、嫁の立場としては葬儀に参列しないのもどうかと思い、有給休暇でお休みをいただきました。
忌引き休暇としての扱いになるかどうかは、それぞれの会社で違いがあるようなので、わからない場合は会社へ確認するようにして下さい。
大手の会社では、もっとお休みを頂けることもあるようなので、参考に一般的な忌引き休暇の日数を載せておきます。
- 夫・妻:10日間
- 両親:7日間
- 子ども:5日間
- 自身の祖父母:3日間
- 自身の兄弟・姉妹:3日間
- 配偶者の両親:3日間
- 配偶者の兄弟・姉妹 1日間
- 配偶者の祖父母:1日間
- 叔父・叔母:1日間
大手は本当にこんなにお休みを頂けるのでしょうか?^^;
実際に忌引きとしてMAXのお休みを取っているのかは疑問ですね。
義理の祖父母は何親等になる?
私の場合、義祖母は2親等に当たります。
しかし規定には、血族の2親等までとなっていて、旦那側の義祖母は忌引き休暇には該当しませんでした…。
- 1親等 両親、子ども、配偶者の親
- 2親等 兄弟姉妹、祖父母、孫、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
- 3親等 曾祖父母、叔父叔母、甥姪、曾孫、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥姪、配偶者の叔父叔母
- 4親等 いとこ、大伯父伯母など
義理の祖父母が亡くなった場合は…
結局、私の職場での規定では、義祖母は忌引き休暇には当たらず、有給休暇という形でお休みをいただきました。
嫁としては、やっぱり葬儀に参列したいですよね。
生前、お会いしたことも数回あったし、義母がとても悲しんでいたので、「仕事ですから!」で参列しないのも気が引けました。
私の場合は。
でも、旦那のご両親や義祖母との関係性によってそれぞれの考えがあるので、ここはそれぞれの立場で判断して下さいね。
義理の祖父母が亡くなった場合は、喪中はがきか年賀状か…どっち?

義祖母が亡くなって、忌引き扱いになるのかどうかは、「職場での規定による」ことが分かりました。
これは、忌引きとしての休暇が取れるかどうかの基準です。
だから、ご本人が忌引きや喪中とするのかとは、また違います。
義祖母が亡くなった場合は喪中でOK
一般的には、喪に服す場合は基本的に2親等までと言われているらしいです。
義祖母(2親等)が亡くなったので、我が家は今年は喪中ということになります。
我が家では年賀状は連名で旦那も私も同じものを用意します。
なので、新年をお祝いする年賀状は出せません。
でも、友達とかに喪中はがきだけでは寂しいと感じたり、
年頃の子供の年賀状のやりとりでは、やっぱり年賀状を出したいと思ったり。
喪中の年ってなんだか寂しいですよね^^;
そんな場合には、寒中お見舞いをお勧めします。
寒中見舞いってどんな時に出すの?年賀状が出せない時にもオススメ

寒中見舞いは、喪中の時にも出せます。
喪中で年賀状が出せない場合でどうしても何かご挨拶したい場合は、代わりに寒中見舞いを出してはどうでしょうか。
そもそも寒中見舞いとは、一年で一番寒いとされる時期に相手の体を気遣うメッセージとして贈られるもの。
年賀状の返信や喪中の時にも送ってもいいものなのです。
出す時期は決まっていて、小寒(1月6日頃)から立春(2月3日頃)までとされています。
私も高校生の時に部活の先輩に寒中見舞いを出した記憶があります。
喪中に寒中見舞いを出す時は、新年を祝う言葉を入れなければOKです。
例えば、
寒中お見舞い申し上げます。
寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
年賀状を頂いていましたが、お返事ができずにいました。
実は、○月に義祖母が永眠しましたので、新年のご挨拶ができませんでした。
ご連絡が行き届かず申し訳ありません。
こちらは、年始は家族でゆったりと過ごすことができております。
〇〇ちゃんも体には気をつけて、また皆んなで集まれる日を楽しみにしています。
では…♡
親しい友人に送る場合は、こんな感じでもいいかなと思います。
寒中見舞いを出す時のポイントはこちらにも書いています。
まとめ
義祖母が亡くなった場合の葬儀は忌引きになるのか?
その年の年賀状や喪中はがきのやりとりについてまとめました。
義祖母が忌引き扱いになるのかは、会社によって異なり、休暇を取得できる日数にもかなり違いがあることが分かりました。
私の職場では忌引き休暇は取得できませんでしたが、有給休暇でお休みを頂くことができたので、無事に葬儀に参列することができました。
このへんの忌引き休暇や葬儀に参列するべきか?については、それぞれの立場がありますので、一概には言えませんが、私は孫嫁として参列できて良かったと思いました。
義祖母が亡くなった今年は、喪中となり年賀状を出すことはできませんが、代わりに寒中見舞いを友人に送ることはできそうです。
義祖母の葬儀について、実際に私が経験した体験談をまとめた記事はこちら↓

孫嫁としての振る舞い、一般的な常識がない私でもなんとか乗り切れました。
お葬式などは経験して段々と分かってくると思うので、こうやって記録を残しておくのも役立つ時がくるかもしれません。
もし疑問とかあれば、遠慮せず質問して下さいね^^
私の経験が役立ちますように…